突然の子どもの発熱や嘔吐、湿疹にどう対応すれば良いのか悩んだ経験はありませんか?特に初めての育児では、不安や戸惑いが大きいものです。そんな時、電話で小児科医や看護師に相談できる#8000は、心強いサポートとなります。本記事では#8000の詳細や利用方法、メリットについて詳しく解説します。
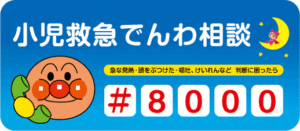
#8000とは?
#8000は、子どもの急な体調不良に対応するための電話相談サービスです。厚生労働省によって平成16年にスタートし、全国の47都道府県で展開されています。固定電話や携帯電話から簡単に利用でき、育児中の保護者を支える便利な仕組みです。
#8000の仕組みと対応時間
電話をかけると、自動的にお住まいの都道府県に転送され、地域の小児科医や看護師が対応します。対応時間は都道府県によって異なり、19:00〜22:00や、19:00〜翌朝9:00などさまざまです。事前に地域ごとの対応時間を確認しておくことをおすすめします。
詳細は以下の厚生労働省公式ページをご確認ください。
#8000と119の違い
#8000は夜間や休日に医療的なアドバイスを提供するもので、緊急時の連絡先ではありません。一方で、子どもの意識がない、呼吸が弱い、大けがをした場合などは迷わず119に連絡してください。119では救急車の要請が適切か判断もしてくれます。
子どもの症状確認ポイント

- 顔色が悪く元気がない
- 息苦しそうで咳が止まらない
- 湿疹や水泡がある
- 便や尿の異常がある
#8000に電話する際の流れ
① 子どもの症状を説明
② 子どもの年齢・性別を伝える
③ 症状に応じた対処法をアドバイス
④ 必要なら病院や救急車の手配
#8000に繋がらない場合
#8000が混み合っている場合は、「子どもの救急」ウェブサイトを活用してください。年齢や症状を選択すると、適切な対処法が案内されます。
その他の対策はこちらの記事もご参照ください:
#7119とは?#8000との違い
#7119は、すべての住民を対象とした救急相談サービスです。急な病気やケガの際、救急車が必要かどうかを判断する際に活用できます。対応地域は限定的ですが、利用可能な場合は便利なサービスです。
まとめ
#8000は子どもの急な病気やケガに対応するための頼れる相談窓口です。まだ認知度が低い状況ですが、多くの家庭で利用されることで安心して子育てができる環境づくりに繋がります。ぜひ周囲の方にもこのサービスをシェアし、いざという時の備えとして活用してください。




